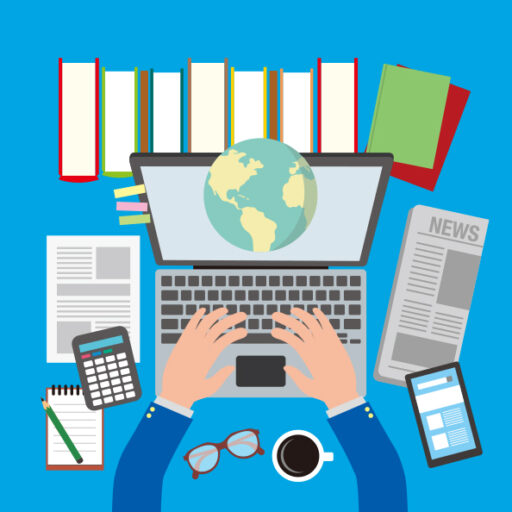書籍の基本情報
原題:Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software
著者:スティーヴン・ジョンソン(Steven Johnson)
出版年:2001年(原著)/ 2004年(日本語版)
副題:蟻・脳・都市・ソフトウェアの自己組織化ネットワーク
内容要約:創発とは何か
1. 創発の定義
創発(emergence)とは、単純なルールに従って行動する個々の要素が相互作用することで、予測できない複雑で高度な秩序やパターンが自発的に現れる現象を指します。
ジョンソンが示す創発の核心的な特徴:
- トップダウンではなくボトムアップ:中央の指令者や設計者なしに秩序が生まれる
- 局所的相互作用がグローバルな秩序を生む:隣接する要素同士の単純なやり取りが、全体として複雑な振る舞いを作り出す
- 部分の総和を超える全体:個々の要素の性質からは予測できない、新しい性質が全体に現れる
- 自己組織化:外部からの命令なしに、システムが自ら組織化する
2. 本書の構成:4つの創発システム
ジョンソンは、一見無関係に見える4つの領域で創発がどのように機能しているかを詳細に分析します。
1. 蟻(アリ)のコロニー
アリのコロニーには女王を含め、全体を統率する「司令官」は存在しません。しかし、数万〜数百万匹のアリの集団は、驚くべき知性を発揮します:
- 最短経路でエサ場を見つける
- 適切な温度管理のために巣を調整する
- 効率的な労働分担を実現する
- 外敵への組織的な防御
鍵となるメカニズム:
- フェロモン通信:アリは化学物質(フェロモン)を残し、それが他のアリの行動を誘導する
- 正のフィードバック:良い経路ほど多くのアリが通り、さらに多くのフェロモンが蓄積される
- 単純なルール:各アリは「フェロモンの濃い方向に進む」という単純な規則に従うだけ
個々のアリは愚かでも、集団としては「群知能(swarm intelligence)」を持つのです。
2. 脳とニューロン
人間の脳には約860億個のニューロン(神経細胞)がありますが、個々のニューロン自体に「意識」や「思考」はありません。しかし、これらが複雑なネットワークを形成することで、意識、記憶、感情、創造性といった高次の精神機能が創発します。
重要な洞察:
- 分散処理:脳には「思考の中央司令部」は存在しない
- 可塑性:ニューロン間の接続は経験によって常に変化する
- パターン認識:膨大な数の微弱な信号が統合されてパターンが認識される
ジョンソンは特に、日本の研究者・中垣俊之らによる「粘菌の迷路解き実験」を詳しく紹介します。脳を持たない単細胞生物である粘菌(菌類や動物、植物のどれにも属さない独特の生物)が、迷路の最短経路を見つけ出す——これは創発の驚くべき実例です。
3. 都市の自己組織化
都市は中央計画だけで作られるのではなく、無数の個人の意思決定が相互作用することで、特有のパターンやエコシステムを創発させます。
都市における創発の例:
- 自然発生的な商業地区:特定の業種が集積するエリア(シリコンバレー、ニューヨークのガーメント地区など)
- 交通流(道路上を走る多数の車両を流れとして捉えた概念で,渋滞現象などを分析するのに適したもの)のパターン:渋滞の波、人流の最適化
- 文化的多様性:移民コミュニティの形成と進化
- スラムの発展:無秩序に見えて実は機能的な構造を持つ
ジョンソンは、ジェイン・ジェイコブズの『アメリカ大都市の死と生』を引用しながら、トップダウンの都市計画がしばしば失敗する理由を説明します。活力ある都市は、住民の自発的な相互作用から生まれるのです。
マンチェスターの事例: 産業革命期のマンチェスターは、計画なしに急速に成長した都市の典型です。混沌としながらも、労働者の住居、工場、商業施設が自己組織化的に配置され、機能的な都市システムが形成されました。
4. ソフトウェアとAI
デジタル世界でも創発は重要な役割を果たしています。
具体例:
- セルオートマトン:コンウェイの「ライフゲーム」では、単純なルールから複雑なパターンが無限に生成される
- 遺伝的アルゴリズム(問題を解決するための手順や計算方法):ランダムな変異と選択を繰り返すことで、最適解が創発する
- 群知能アルゴリズム:蟻や鳥の振る舞いを模倣した最適化手法
- ニューラルネットワーク:脳の構造を模倣した機械学習システム
ジョンソンは、初期のウェブがどのようにリンク構造を通じて自己組織化し、検索エンジンがその創発的秩序を活用したかを論じます。
3. 創発システムの共通原理
ジョンソンは、これら異なる領域に共通する創発の原理を抽出します:
- 多数の相互作用する主体:システムは多くの個別要素から構成される
- 局所的情報に基づく行動:各要素は近隣の情報のみに基づいて行動する
- 単純なルール:個々の要素が従うルールは比較的単純
- フィードバックループ:正と負のフィードバックが秩序を生む
- 時間の経過:創発は瞬時には起こらず、時間をかけて展開する
- 適応と学習:システムは環境に応じて変化する
深い考察:創発が現代世界に与える示唆
1. 組織論への革命的視点
伝統的組織 vs 創発的組織
従来の組織論は、トップダウンの階層構造を前提としてきました:
- 経営者が戦略を立案
- 中間管理職が実行を監督
- 現場が指示に従う
しかし、創発の視点は全く異なる組織像を提示します:
創発的組織の特徴:
- 分散型意思決定:現場に権限を委譲し、局所的な最適化を促す
- 自律的チーム:中央の命令ではなく、チーム間の相互作用が全体の秩序を生む
- 適応的戦略:固定された計画ではなく、状況に応じて進化する戦略
実例:バルブ社のフラット組織
ゲーム会社のバルブ(Valve)は、管理職を置かず、社員が自由にプロジェクトを選べる完全にフラットな組織です。これは創発的組織の極端な例ですが、『Portal』や『Half-Life』などの革新的ゲームを生み出しています。
アジャイル開発(短期間での反復開発を繰り返すことで、柔軟かつ迅速に変化に対応する開発スタイル)との共鳴
ソフトウェア開発におけるアジャイル手法は、創発の原理を実践に移したものと言えます:
- 詳細な計画よりも、反復的な改善
- トップダウンの指示よりも、チームの自己組織化
- 固定された役割よりも、流動的な協働
2. イノベーション理論への貢献
「隣接可能性(Adjacent Possible)」
革新的な技術や発想によって新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらすイノベーション。
ジョンソンは後の著作『イノベーションのアイデアを生み出す七つの法則』でこの概念を展開しますが、その萌芽(物事が起ころうとする兆候)は『創発』にあります。
隣接可能性とは: 現在の状態から一歩だけ進める範囲にある、まだ実現していない可能性の領域。イノベーションは、既存の要素の新しい組み合わせから創発するのです。
歴史的事例:
- グーテンベルクの印刷機:ワイン圧搾機、金属活字、インクなど既存技術の創発的組み合わせ
- インターネット:パケット交換、TCP/IP、ハイパーテキストなどの要素が相互作用して創発
パケット交換:データを小さな「パケット」という単位に分割し、宛先や順序などの情報を付けて送信する方式。TCP/IP:インターネットの基盤 となる 、コンピュータ同士が通信を行う際のルール。ハイパーテキスト:複数の文書を相互に関連付ける仕組み。
「流動的ネットワーク」環境の重要性
イノベーションが起こりやすい環境には、創発的な特徴があります:
17世紀ロンドンのコーヒーハウス:
- 異なる背景を持つ人々が偶然出会う
- アイデアが自由に交換される
- 階層や肩書きが薄れる
- 長時間の対話が可能
これは現代の「シリコンバレー」や「オープンイノベーション」の原型です。
シリコンバレー:西海岸カリフォルニア州。シリコンバレーは正式な地名ではなく、IT関連企業が集積したエリア一帯の通称。オープンイノベーション:自社内のイノベーションの効率化達成の為に、自社以外も含めたあらゆるリソースを活用して市場機会の増加を目指すこと。
3. AI・機械学習への深い洞察
ディープラーニングと創発
現代のディープラーニング(コンピューターが自律的に考えて学ぶ技術)は、まさに創発現象です:
- 個々のニューロン(パーセプトロン:人間の脳にある神経細胞ニューロンのネットワークを模倣した数理モデルの一種)は単純な計算しかしない
- しかし、数百万〜数十億のパラメータ(変化できる数。スマートフォンのタイマー機能のA時BC分のABC)が相互作用することで、画像認識、自然言語理解、創造性すら示す
興味深い問題: なぜニューラルネットワーク(脳の神経回路の動作を模した数理モデル)が機能するのか、数学的に完全には説明できていません。これは、創発システムの本質的な予測不可能性を示しています。
GPT、Claudeなどの大規模言語モデル
大規模言語モデル(LLM:入力した文章に対して続きを生成できるAI)は、創発の驚くべき実例です:
- 学習時:膨大なテキストデータから統計的パターンを学ぶ
- 創発する能力:設計者も予期しなかった能力(推論、コーディング:コンピューターが理解できるようにプログラミング言語を使って命令を書き込む作業、創作など)が現れる
これは、システムが十分に複雑になると、設計意図を超えた性質が創発することを示しています。
AGI(汎用人工知能)への示唆
もし真の人工知能(AGI:人間の知性と同等と見なされ、私たちの知能に匹敵するAI)が実現するとすれば、それはトップダウンで「意識をプログラムする」のではなく、十分に複雑なシステムから意識が創発する形になるでしょう。
4. 社会変革と政治への示唆
中央集権 vs 分散型システム
創発の視点は、政治・経済システムに対する根本的な問いを投げかけます。
中央計画経済の失敗: ソ連の計画経済が失敗した理由の一つは、創発を無視したことです。中央の計画者が全てを設計しようとしても、無数の個人の局所的ニーズや創意工夫から生まれる創発的秩序には敵わないのです。
市場経済の創発性: アダム・スミスの「見えざる手」は、創発の古典的な例です。個々の経済主体が自己利益を追求することで、意図せず全体として効率的な資源配分が実現される——これは創発そのものです。
Web3、DAO、ブロックチェーン
現代のブロックチェーン技術と分散型自律組織(DAO)は、創発の原理を意識的に応用しようとする試みです:
- 中央管理者なしに機能するシステム
- スマートコントラクト(自動的に実行される契約)による自律的な取引
- 参加者の相互作用から秩序が生まれる
Web3:分散型、ユーザー主権、所有権の明確化がキーワード。Web1.0:情報の閲覧が中心。Web2.0:SNSやブログなど双方向のやり取りが可能。DAO分散型自律組織:特定の管理者や中央集権的な主体が存在せず、ブロックチェーン上に記録されたプログラムに基づいて、参加者全員の合意形成によって自律的に運営される組織。ブロックチェーン:デジタルデータを安全に管理するための革新的な技術。
草の根運動とソーシャルメディア
「アラブの春」や「#MeToo運動」などは、中央の指導者なしに自己組織化した社会運動です。ソーシャルメディアは、個人の局所的な発信が相互作用し、グローバルな影響を持つ運動へと創発する基盤を提供しました。
アラブの春:2010年12月にチュニジアで始まった民主化運動の総称、エジプトではムバラク政権、リビアではカダフィ政権、イエメンではサレハ政権が相次いで倒された。#MeToo運動:これまで沈黙してきた被害者がセクハラや性的暴力の経験を告白・共有し、声を上げる国際的な運動。SNSのハッシュタグ(#)機能を利用して被害を告白、拡散するという動き。
5. 教育への示唆
従来の教育モデルの限界
伝統的な教育は、トップダウンで知識を「注入」するモデルでした:
- 教師が知識を持つ
- 生徒は受動的に受け取る
- 標準化されたカリキュラム
創発的学習環境
創発の原理に基づく教育は、全く異なります:
- プロジェクトベース学習:生徒同士の相互作用から学びが創発
- 反転授業:一方的な講義ではなく、議論と探究を中心に
- 遊びと探索:子どもの自発的な好奇心から学習が創発する
モンテッソーリ教育の創発性: マリア・モンテッソーリの教育法は、子どもの自己組織化能力を信頼し、準備された環境の中で自由に探索させます。これは創発的教育の実践例です。
子供は自ら育つ「自己教育力」があることを前提とした教育法。1.子どもの自立を促す環境を用意する。-子どもの手の届く位置に服が置いてある。-子どもの服だけでまとまっている(父母の服などと混ざっていない)。-トップスやズボン、靴下など分類されて置かれている。-多すぎたり、少なすぎたりせず、選ぶのに適切な数・枚数で置かれている。2.大人の「やらせたい」でなく、子どもの「やりたい」を大切にする。3.自己選択できる関わりや声かけをする。4.「叱る」は「伝える」に、「褒める」は「認める」に。
6. 創造性と芸術
創造性は個人の天才か、それとも創発か?
伝統的な芸術観は「孤高の天才」を称賛してきました。しかし、創発の視点は異なる理解を提供します。
芸術運動の創発:
- 印象派:個々の画家の実験が相互作用し、新しい様式が創発
- ジャズ:即興演奏での相互作用から、予測不可能な音楽が生まれる
- ハリウッド映画:脚本家、監督、俳優、編集者などの創発的協働
集合的創造性: 真の創造性は、しばしば個人の頭脳内での「アイデアのネットワーク」と、他者との「社会的ネットワーク」の両方における創発から生まれます。
7. 哲学的・存在論的問い
意識は創発するのか?
脳科学と哲学における最大の謎は「意識のハードプロブレム(難問)」です。ニューロンの電気化学的活動から、なぜ主観的な経験(クオリア:感じることそのもの、酸っぱいとか真っ赤だなとか主観的な感覚の中身)が生じるのか?
創発主義の立場: 意識は、脳の複雑な情報処理から創発する高次の性質である。部分(ニューロン)には意識はないが、全体のレベルで新しい性質として現れる。
還元主義との対立: 還元主義者は「意識も結局は物理法則に還元できる」と主張しますが、創発主義は「部分の総和では説明できない真に新しい性質が現れる」と主張します。
自由意志と決定論
もし私たちの思考や行動が、脳内のニューロンの相互作用から創発するなら、「自由意志」は存在するのでしょうか?
相互作用主義的自由意志: 創発の視点は、古典的な二元論(心と脳は別物)でも、単純な決定論でもない第三の道を示唆します。意識は脳から創発するが、創発したレベルでは独自の因果力を持つ——これは「下向き因果(downward causation)」と呼ばれます。
下向き因果:自分自身が自分自身に対して因果的効力を持つ自己因果の1つです。全体がそれを構成する部分に対して因果的効力を持つとする自己因果の1つです。下向き因果の理論は、すべての心的現象の科学的説明の基礎理論となると期待されます。下向き因果の仕組みとは、物理的には脳で在りながら、それを構成するニューロン1つ1つが持たない因果的効力を持つ仕組み。
生命とは何か
生命も、化学物質の創発的組織化の産物です:
- DNA、RNA、タンパク質、脂質などの分子
- これらが相互作用して細胞が形成される
- 細胞が組織化して生物になる
- 生物が相互作用して生態系が創発する
生命の定義の難しさ: どこまでが「単なる化学反応」で、どこからが「生命」なのか?この境界は曖昧で、創発は連続的なプロセスであることを示唆します。
DNA:二重螺旋構造で機能の長期保存。RNA:通常は単一鎖で短期の情報伝達、安定性よりも柔軟性と処理速度が重視されている。どちらも遺伝情報を運ぶ分子。
8. 予測不可能性と謙虚さ
創発は予測できるか?
創発システムの最も重要な特徴の一つは、原理的な予測不可能性です。
複雑系の三体問題: 太陽、地球、月のような3つの天体の運動ですら、長期的には予測不可能です(カオス理論)。ましてや、数億の要素が相互作用するシステムの振る舞いを正確に予測することは不可能です。
謙虚さの必要性: これは、計画者、経営者、政策立案者に謙虚さを求めます:
- 完璧な計画は不可能
- 予期せぬ結果が常に生じる
- 柔軟性と適応能力が重要
「神の視点」の放棄
創発の世界観は、全知全能の観察者という概念を放棄します。システムの外側から全てを見渡し、完全に理解し、コントロールする——そんな立場は存在しません。
私たちは常に、システムの一部であり、局所的な視点しか持ち得ません。しかし、それでも集団として知恵が創発し得るのです。
批判的考察と限界
1. 創発概念の曖昧さ
批判者は、「創発」という概念が曖昧で、説明力に乏しいと指摘します:
- 何が創発で、何がそうでないのか、明確な基準がない
- 「創発」と言えば何でも説明した気になる危険性
2. 還元主義との対立
科学の基本方法論は還元主義です。複雑な現象を単純な要素に分解して理解する。創発主義は、この方法論に挑戦するものですが、両者の調和は容易ではありません。
3. 倫理的責任の問題
もし組織や社会の問題が「創発の結果」なら、誰が責任を取るのでしょうか?創発概念は、責任の所在を曖昧にする危険性があります。
4. デザインの役割
ジョンソンは創発の自然発生的側面を強調しますが、実際には「創発を促すデザイン」も重要です。完全に設計しないことと、全く設計しないことは違います。
デザイン:何かを作る前に意図を持ち、目的に合わせて形や機能を計画・構成すること。美的要素、使いやすさ、効率性、心理的影響も含む。何かをつくる際に偶然ではなく、明確な目的と狙いがある。偶然ではなく、理由のある形をつくること。
現代的関連性:2025年の視点から
1. ChatGPT以降のAI時代
大規模言語モデル(LLM:入力した文章に対して続きを生成できるAI)の登場は、創発の劇的な実例を提供しました。誰も「ChatGPTが詩を書ける」ようにプログラムしていないのに、そうなったのです。
2. パンデミックと創発的対応
COVID-19パンデミックへの対応は、トップダウンの政府指示と、ボトムアップの市民の自己組織化(マスク製作、相互扶助など)の組み合わせでした。どちらか一方では不十分だったでしょう。
3. 気候変動と複雑系
気候システムは究極の創発システムです。無数の要因が非線形に相互作用し、予測困難な「ティッピングポイント(少しずつ変化していた物事が急に大きく変化する転換点)」が存在します。創発の理解は、気候対策に不可欠です。
4. メタバース・仮想世界
『フォートナイト』や『マインクラフト』などのゲーム内で、プレイヤーの相互作用から独自の文化、経済、社会が創発しています。これは未来の社会システムの実験場かもしれません。
フォートナイト:100人で島に降り立ち、武器を集めながら生き残りをかけて戦うゲーム。マインクラフト:ブロックを組み合わせて作られた世界を冒険し、一から自分だけの世界を作り上げる、目的や縛りのない自由なゲーム。
結論:秩序は下から生まれる
スティーヴン・ジョンソンの『創発』が提供する最も深い洞察は、秩序は必ずしも上から設計されるのではなく、下から自然に生まれるという理解です。
この認識は、私たちに以下を求めます:
- 謙虚さ:完璧にコントロールできるという幻想を捨てる
- 信頼:人々の自己組織化能力を信じる
- 環境整備:創発が起こりやすい「隣接可能性」に富んだ環境を作る
- 観察と適応:計画に固執せず、創発するパターンに注意を払い、適応する
- 多様性の尊重:創発には多様な要素の相互作用が必要
21世紀の複雑な課題——気候変動、パンデミック、経済格差、AI統治——に対処するには、トップダウンの管理だけでは不十分です。創発の知恵を活用し、ボトムアップの創造性と適応力を解き放つ必要があります。
ジョンソンが示したのは、単なる科学理論ではなく、世界の見方の革命です。蟻、脳、都市、ソフトウェア——これらすべてが教えてくれるのは、真の知性と秩序は、中央の司令官ではなく、無数の小さな相互作用から生まれるということです。
私たち一人ひとりは、より大きな創発システムの一部です。そして、その認識こそが、より良い未来を創発させる第一歩なのかもしれません。
推薦文献
『創発』をより深く理解するための関連書籍:
- 『複雑系』 – M・ミッチェル・ワールドロップ:創発の科学的背景
- 『アメリカ大都市の死と生』 – ジェイン・ジェイコブズ:都市の創発的秩序
- 『蟻の自然誌』 – バート・ヘルドブラー、エドワード・O・ウィルソン:群知能の生物学
- 『心の社会』 – マーヴィン・ミンスキー:脳と意識の創発理論
- 『イノベーションのアイデアを生み出す七つの法則』 – スティーヴン・ジョンソン:創発とイノベーション
- 『シンク・コンプレックス』 – ドネラ・メドウズ:システム思考入門
創発という視点は、あなたの周りの世界を全く新しい目で見る扉を開いてくれるでしょう。
補足情報
この書籍は、ローカルな相互作用から生まれるグローバルな秩序を解明し、脳のない粘菌が集団では迷路を解き、迷子のアリが豊かなエサ場を見つけるという創発現象を扱っています。
特に重要なポイント:
- 現代的関連性:ChatGPTなどのAIの能力も、まさに創発現象です。誰も「会話ができるように」とプログラムしていないのに、大量のパラメータの相互作用から会話能力が創発しています。
- 実践的応用:組織運営、イノベーション創出、都市計画、AI開発など、幅広い領域で創発の原理を応用できます。
- 哲学的深み:意識、自由意志、生命といった根源的な問いにも、創発は新しい視点を提供します。
以上。
好きなことから始まる、幸せの連鎖
あなたが好きなこと
面白そうだと思うこと
楽しそうに見えること
興味があること
やってみたいこと
子供の頃好きだったこと
ここにはあなただけの宝物があります。
例えば、絵を描くのが好きだったなら、Webデザイナーのスキルを身に付けてみる。
スキルを身に付けたら、
高収入を得られる会社に就職する
身に付けたスキルを使ってリモートワークで好きな場所で働く
副業としてスキルを活かして収入を得る
セミナー講師として、あなたの知識を次の世代に伝える
AIを活用してクリエイティブな動画を作る。
あなたの選択肢は、今よりずっと豊かになります。
もしかしたら、あなたの収入は今よりも増えるかもしれません。
時間に余裕が生まれるかも
心に余裕やゆとりの気持ちが生まれるかも
新しい可能性が見えてくるかもしれません。
あなたが好きだったことを「スキル」という道具に変えただけで、あなたの人生は確実に動き始めます。
動き始めたら、更に、あなたらしく振る舞うことが大切です。
あなたが、あなたらしくなる為には勇気が必要かもしれません。
頑張ってください!
少しだけ勇気を出してください!
恥ずかしいと思ってないでしょうか?
照れくさいと思ってないでしょうか?
こんなこと出来ないと思ってないでしょうか?
人の目を気にして、流されているだけではないでしょうか?
皆と同じなら大丈夫だと思ってないでしょうか?
本当のあなたを隠してないでしょうか?
目の前にある、あなたの殻を打ち破る必要があるのではないでしょうか?
あなたが豊かになったら、あなたの心にはゆとりが生まれ、あなたの周りにいる人に優しい言葉をかけてあげることができるのに、
親切にしてあげることができるのに、
手を貸してあげることができるのに、
差し出すことができるのに、
分け合うことができるのに、
応援してあげることができるのに、
励ましてあげることができるのに、
いたわってあげることができるのに、
笑顔を見せてあげることができるのに、
ありがとうと言うことができるのに。
あなたの小さな行動が、大きな波紋を生み出すことができるのに、
あなたの周りにいる人が、優しさで満たされるのに、
イイ感じがする空気で、空間が満ちるというのに、
喜びで満たされるのに、
感謝の気持ちで満たされるのに、
愛で満たされるのに、
あなたの小さな行動が、隣にいる誰かを幸せにすることができるのに。
愛が目の前にあるのに、
ただ、気がついていないだけなのに、
ただ、素直になれないだけなのに、
あなたの周りにいる人が愛で満たされたなら、あなたがいる環境が今よりもずっとよくなるのに、
心地のよい空間になるというのに、
「イイ感じ」と思える瞬間が増えるのに、
幸せを感じる時間が増えるのに、
あなたは今よりもっと幸せな人になるのに。
あなたが幸せになればなるほど、あなたの周りにいる人も気持ちに余裕が生まれます。
幸せを感じる瞬間が増えます。
幸せな人に変わります。
あなたには良い循環を生み出すことができます。
良い循環の輪を少しずつ、そして、確実に広げていくことができます。
そんな風に、人生を豊かにして、イイ感じで生きるのも悪くないですよね。
あなたが幸せになる、そして、あなたの周りにいる人も幸せになる。
イイ感じだと思いませんか?
子供の頃、夢中になっていた事は何ですか?
今、心がワクワクすることは何ですか?
思わず、気持ちが惹かれてしまうことは何でしょうか?
好きなことについて調べてみた、それも悪くはないですね。
スキルを学べる場所を探してみた、それも悪くはないですね。
昔、好きだったことをもう一度やってみた、そんなのも“あり”ですね。
あなたと周りにいる誰かの「人生を変えるかもしれない、小さな一歩」を踏み出してみた、それも悪くはないですね。
あなたには世界を変える力があります。
あなたは幸せになって、笑顔になって、誰かの希望になって、良い循環を生み出します。
イイ感じがする人生、ここから始めてみるのも悪くはないですよね。